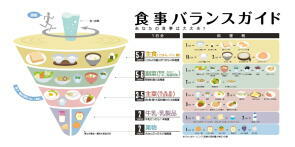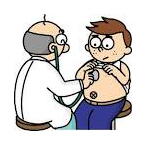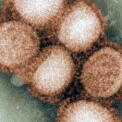| 脳の病気の種類 |
各疾患の説明 |
| ドライアイ |
ドライアイになると、目が乾くといった症状以外にもさまざまな不快な症状があらわれます。例えば、10秒間目を開いた状態を保つことができない場合も、ドライアイの可能性が高いといわれています。症状が重くならないうちに、眼科で治療を受けることが必要です。 |
| VDT症候群 |
VDT症候群とは、パソコンなどのディスプレイ(VDT:ビジュアル・ディスプレイ・ターミナル)を使った長時間の作業により、目や身体や心に影響のでる病気です。 |
| アレルギー性結膜炎 |
アレルギー性結膜炎は、アレルギー反応によって目の粘膜に炎症が起こった状態で、アレルギー性鼻結膜炎とも呼ばれます。目のかゆみ、流涙、めやに、異物感、結膜充血、まぶたの腫れなどの症状が現れます。なかでも、かゆみが特徴的で、アレルギー性鼻炎の症状をともなうことがしばしばあります。 |
| 感染性結膜炎 |
感染性結膜炎は、細菌やウイルスが目に感染し、白目の一番表面の膜である結膜に炎症を起こす病気です。目に不快な症状があらわれることがほとんどですが、プール熱のように目の症状だけでなく、のどの痛みや発熱といった、かぜに似た症状を引き起こすこともあります。 |
| ものもらい |
麦粒種ともいい、まぶたにあるマイボーム腺やまつ毛の根もとの脂腺の急性化膿性炎症。マイボーム腺にできるものを内麦粒腫、まつ毛の根もとにできるものを外麦粒腫という。主に黄色ブドウ球菌の感染を原因とし、まぶたの裏側などが腫れて痛む病気。 |
| 感染性角膜炎 |
角膜に感染する病原体として、細菌、ウイルス、真菌、アカントアメーバがあり、これらを総称して感染性角膜炎と呼んでいます。
感染性結膜炎に比べ、角膜炎は重く、治療を怠っていると視力障害を残したり、角膜が穿孔(穴があく)して、角膜移植などの手術が必要になるケースもあります。 |
| 飛蚊症 |
目の前に蚊(か)が飛んでいるように見える症状をいいます。
原因としては、後部硝子体剥離(こうぶしょうしたいはくり)などがあります。
病気でないことが多いのですが、網膜剥離(もうまくはくり)や硝子体出血(しょうしたいしゅっけつ)がおこっていることもあり、眼底検査を受ける必要があります。 |
| 緑内障 |
緑内障は網膜神経節細胞が死滅する進行性の病気で、特徴的な視神経の変形と視野異常(視野欠損)を生じます。現在の医療技術では一度喪失した視野は回復させることが困難なため、失明の原因となります。
日本では、最近になって糖尿病網膜症を抜いて1番目の失明の原因となっています。視野狭窄は自覚したころには末期症状に至っていることが多く、早期発見には定期的な健康診断が重要となります。 |
| 白内障 |
水晶体を構成する蛋白質(クリスタリン)が変性し、黄白色または白色に濁ることにより発症します。しかし、根本的な原因は解明されておらず、水晶体の細胞同士の接着力が弱まったり、水分の通りが悪くなったりして起こるのではないかといわれています。
発症は45歳以上の中年に多く、年齢を重ねるにつれて割合が増加します。また、80歳以上の高齢者はほとんどが何らかの形で白内障の症状を引き起こしているといわれていますが、進行の速さには個人差があり、目が見えづらくなるといった症状に至るとは限りません。 |
| 加齢黄斑変性 |
網膜の中心部直径6000μmの範囲は黄斑とよばれ、ものを見るときに最も大切な働きをします。この黄斑の働きによって私達は良い視力を維持したり、色の判別を行ったりします。この黄斑が加齢にともなって様々な異常をきたした状態を加齢黄斑変性といいます。 |
| 網膜剥離 |
目の内部を満たす硝子体は通常ゼリー状ですが、加齢により一部が液状化し、ゼリー状の硝子体が眼球の動きに連動して移動するようになります。その際硝子体に網膜が引っ張られると、裂け目(裂孔)ができることがあります。裂け目から水が入ると網膜がはがれ、網膜剥離となります。 |
| 糖尿病網膜症 |
糖尿病網膜症とは、糖尿病の3大合併症の一つです。糖代謝異常に伴う眼の網膜などに様々な変化をきたし、視力低下を認め、日本の中途失明の第2位となっています
。 |
| 結膜下出血 |
結膜の一部である、眼球結膜で出血が起こると、いわゆる白目に当る部分が赤くなります。赤くなる範囲は、出血した場所と量によって様々です。 同じく血液の赤色が目立つ症状として充血がありますが、充血した時は毛細血管が広がっているために血管が見えます。結膜下出血の場合は出血部の血管が見えなくなっている点が異なります。 なお、結膜下出血が原因で視力が低下したり視野が狭くなることはなく、もしもそのようなことが起こった場合は、別に原因が考えられます。 |